大豆アレルギーの症状と原因〜醤油やお味噌もダメ?

これらの食品に反応してしまう、大豆アレルギーの症状はどのようなものなのでしょうか?
また、その原因はどこにあるのでしょうか?
ここでは、大豆アレルギーの症状や原因について詳しく解説していきたいと思います。
発症を引き起こすメカニズム
大豆アレルギーは、大豆がアレルゲンとなって引き起こされます。食物アレルギーの中でも卵や牛乳などと同様に多く見られます。
乳幼児から始まることが多く、小学校に上がる前には子どもの体にだいぶ耐性が作られてきて、解決することが多いようです。
スポンサーリンク
大豆は加工食品の主原料や副原料としても広範囲に用いられることが多い食品です。
そのため、毎日子どもに与える食事の中で、大豆を含む食べ物を排除するのはとても大変なことです。

なんといても、日本人にとっての重要な調味料である味噌や醤油が大豆でできていますから、これらを口にすることが出来ないとなると、食事のメニューにかなりの制限がかかることになります。
ただし、幸いなことに大豆アレルギーでの重症例はわりと少ないようです。
アナフィラキシーショックや喘息などの重い症状があらわれるのはとても稀なことです。
そのため、一度発症してもある程度子供が大きくなったら、少しずつチャレンジしてみるといいと思います。
ただし、重症のアトピーを発症している場合には、より慎重に対応した方がいいでしょう。
検査の方法と治療について
大豆アレルギーの検査方法には、血液検査と皮膚テストがあります。
血液検査で「大豆」の項目に反応が見られたら陽性ということになります。
スポンサーリンク
皮膚テストというのは、少量の抗体を皮膚にたらしたり、皮膚を直接針で軽く刺したりしてその反応を見るものや、パッチテストといって、絆創膏のようなものに抗体をつけて皮膚に貼るやり方があります。
いずれの方法も、痛みはほとんどありませんので、小さな子供でも安心して検査を受けることができます。
仮にこれらの検査で陽性が出たとしても、実際に大豆を食べてアレルギー症状が現れない場合には、あえて制限をする必要はありません。
大豆を食べて湿疹などがあらわれ、なおかつ検査が陽性であれば、食事から大豆を除去していく必要があります。
治療の方法としては、その人の症状の重さにあわせて、大豆製品を制限していくことになります。
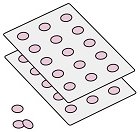
また、薬物療法なども、同時に行われることもあります。
乳児などが発症した場合には、アレルゲンとなる大豆製品を除去して、みそや醤油などの開始を遅らせるようにしましょう。
また、授乳中の母親は、インスタント食品やスナック菓子はできるだけ食べないようにしたほうがいいでしょう。
スポンサーリンク
