青森の方言〜津軽弁と南部弁はまったく異なる言葉

青森には、江戸時代に藩が2つ存在したため、それぞれの地域ごとに大きく二つの方言に分かれています。
弘前藩がおかれた津軽地方では津軽弁が、また南部藩がおかれた南部地方では南部弁が使用されています。
まるで外国語を聞いているような難解さ
一般的に青森方言は難易度が非常に高く、共通語しか理解していない方がこの地域の言葉を耳にすると、まるで外国語を聞いているかのごとくまったく理解できない場合が多いようです。
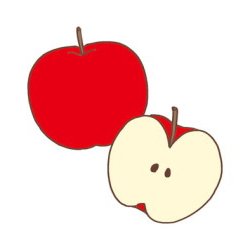
スポンサーリンク
実は、似たような状況が青森県内においても発生しているのです。
というのも津軽弁と南部弁ではそれぞれが独特な言葉になりますので、コミュニケーションは出来るものの意味が通じない場面もあり、同じ青森県民同士でも時には通訳が必要になることもあります。
津軽弁は古い時代に使用されていた大和言葉や北の住民であるアイヌの言葉も混ざり成立したものです。
現代においては使用されることがない古語が含まれていることから、他県の方には意味が通じにくくなっています。
発音される音を見たときにシ・ス、チ・ツ、ジ・ズなどの言葉の区別がないことが大きな特徴になります。
そのため「寿司:すす」「獅子:すす」などと非常に分かりづらいことになります。
また南部弁は津軽弁と比較するとイントネーションが緩やかな特徴があり、丁寧な表現が音場の終わりに多く付くためやや女性的に聞こえることもあります。
▲蟹田駅で聞いた地元の人々ならではの会話がおもしろいです
独特の発音の仕方が特徴的
言語としてみたときに、津軽弁の特徴としては語中や語尾にあるカ行・タ行が濁音になりガ行・ダ行に変化する場合があります。
スポンサーリンク
いくつか例をあげてみましょう。
「イカ:イガ」「みかん:みがん」「いちご:いぢご」
などのような感じで濁ります。
珍しいところでは共通語では使用することがない「クヮ・グヮ」の発音を用いることがあります。
たとえば「元日:グヮンジツ」「生姜:ショウグヮア」などと発音します。

また語中にンが挿入されて撥音を多く使うこともあります。
たとえば「油:あんぶら」「すじこ:すんずご」などと発音します。
フランス語のように聞こえる場合があります
具体的な単語例としては次のようなものがあります。
「どうしようもない:どもなんね」「うるさい:しゃしね」「いらっしゃい:おいであれ・こいへ」「恥ずかしい:めぐせぇ・しょす」「寒かった:さぶふてあった」
などのように表現します。
また青森の方言はあまりにも標準語とかけ離れていることからフランス語のように聞こえる場合もあります。
最近ではテレビCMでネタとして使われるなど知名度は高いのですが、その一方でネイティブの青森県人でなければなかなか意味を理解できません。
スポンサーリンク
