静岡の方言の特徴と独特の表現

ここでは、静岡の方言に関するうんちくについて書いてみたいと思います。
歴史とルーツに関するうんちく
静岡はかつての旧令制国で伊豆国・駿河国・遠江国などの3国に相当する地域になり、県内全体で使用されている言葉を静岡弁として認識されることもあります。
しかし、狭義では県中部で話されている言葉のみを指す場合もあります。
かつては3国に分かれていたことから地域ごとに文化や風習が異なり、住民の意識の違いや言葉についてもそれぞれに差異があります。
スポンサーリンク
静岡弁を細かく分けたときには東部・中部・西部・井川などの方言の種類があげられます。

またこれ以外にも、県西部では遠州弁も用いられています。
東部方言はおもに伊豆半島を含む沼津市以東で用いられ、中部方言は富士市以西から掛川市以東で用いられています。
また西部方言は袋井市や森町以西で使われ、井川方言は大井川上流に所在した旧井川村などで用いられている言葉になります。
さらに遠州弁はかつての遠江国である県西部地区で使われており、日本国内の方言を東西に分ける際の境界とされています。
標準語に近い部類
静岡弁を言語としてみたときの特徴としては、首都圏にも近いことから共通語に非常に近い部類に入ります。
音韻やアクセントなどを細かく見ても大きく変わることはなく、他の地方から訪れた人でも話が通じないということはまずありません。
スポンサーリンク
ただ県内でも西部に行けば行くほどに関西方面の言葉が多く聞かれるようになり、「〜いる→〜おる」「〜ない→〜ん」のような感じで変化が見られるようになります。
また静岡弁の特徴として推量表現で、ら・だら・ずら、が用いられることが多く若い世代にも引き継がれています。
実際に会話をする中では、共通語と比較して変化はそれほどないのですが、個々の言葉で大きな違いが見られます。
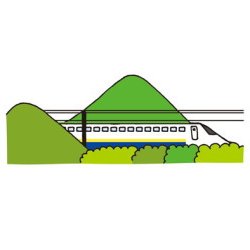
「がんこ:すごく・たくさん」「けっこい:きれい」「しょんない:仕方がない」「〜だけん:〜だかど」「〜だで:〜だから」「貸す:かせる」
いずれも意味をあらかじめ理解していなければ、会話の途中で話が通じなくなることもあります。
また静岡は国内の方言を東西に分ける際の境界である点が大きな特徴になるのですが、これは言葉だけでなく日本人の好みや考え方の東西の違いが平均化されている地域としても知られています。
そのため、企業では新商品を発売する際には同地でモニター試験を行い、商品開発に反映させたり発売の可否を決めることが非常に多いようです。
全国に先んじて商品が発売されることもありますので、気になる方はぜひチェックしてみてるといいでしょう。
スポンサーリンク
