鹿児島の方言〜その難解さゆえに暗号として使われた?

薩隅方言とは、現在の鹿児島県の位置がかつての薩摩国と大隅国にあたることからその名称がつけられており、地域としては鹿児島県から宮崎県の南西部にまで至ります。
しかし、奄美群島に関してましては、その範囲から除かれます。
宮崎県の南西部の地域で使用されているのは薩摩方言の累系ともいえるもので、諸県地方を含め言葉は諸県弁と呼ばれることもあります。
薩摩では肥筑ことばから多く用いられている
スポンサーリンク
薩摩地方は同じ域内においても、土地により語彙や言い回しに大きな違いがあります。
特に薩摩半島の枕崎市で使われている言葉は、他の地域の人にはまったく相容れない言葉がある場合も多いようです。
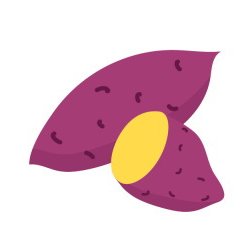
地域と地域の行き来が激しい現代においても、言葉が通じないことや勘違いによるトラブルが生じることも少なからずあると言われています。
また一般的に九州弁については「よか」「ばってん」などの表現が多く使われていると思われがちです。
しかし、これらの表現に関しては中・北部九州地域で広く使われている肥筑方言で多く用いられているものです。
一方で薩隅方言においては、子音で終わる語が発達しており、この点において双方には大きな違いがあります。
▲オーダー後の店員さんの言葉が鹿児島弁です
アクセントで分かる地域の例
鹿児島弁を言語としてみたときの特徴を考えてみましょう。
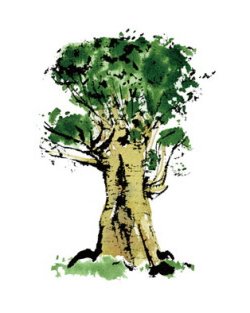
また小林市や都城市、末吉市、志布志市などの地域においては、統合一型式アクセントが用いられます。
さらに北諸県郡と西諸県郡においては、無アクセントとなります。
音韻に関してはaiの発音がeに変化することもあります。
スポンサーリンク
たとえば、「灰→ヘイ」「貝→ケイ」「大根→デコン」「書いた→ケタ」などと発音します。
それ以外の具体的な単語の事例としては、次のようなものがあります。
「おつかれさま:おやっとさあ」「がんばれ:きばれ」「うるさい:せがらし」「ありがとうございます:あいがとさげもした」「おいしい:うんめ」「いつのまにか:いっのこめ」「もったいない:あったらし」
などがあげられます。
薩摩地方は、かつての明治維新において薩摩出身者の多くが役人などとして東京で働いたことがあるため、特に警察官となった出身者が一般市民と関わりあう中で次第に標準語として取り入れられた薩摩の言葉がいくつか存在します。
またこの地方の言葉を難しく感じさせている一つの要因として早口であることがあげられます。
そのため、第二次世界大戦では暗号代わりに用いられたこともあります。
スポンサーリンク
